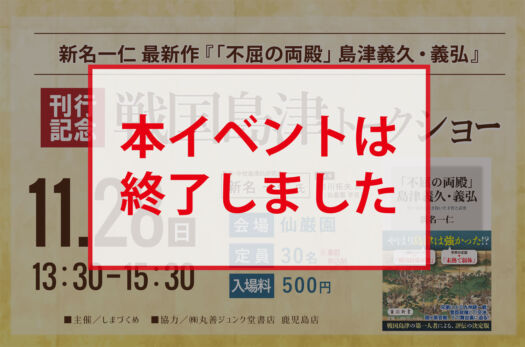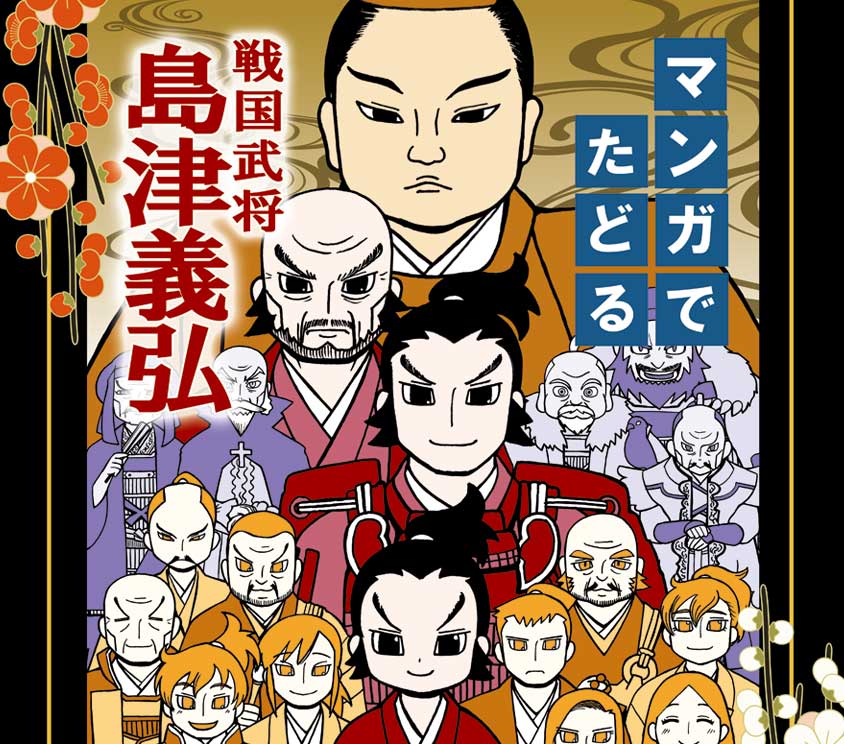大盛況の会場の様子
島津の「強さ」の本質 強い島津氏のイメージ…、高城合戦や戸次川の戦いでの見事な勝ちっぷり、関ヶ原での敵中突破…
通説や風説が入り交じり、ゲームや漫画の影響などもあり、一般的にはこういったイメージを持った人が多いと思います。その一方で「全国の大名の中でも弱い大名の代名詞」という見方をした近代史研究者の分析する戦国島津像があります。 何故こんなに大きく違うのでしょうか?
又はそれはどんな史料を元に分析されたものなのでしょうか? そこを知るに大きく関わってくるのが16代当主島津義久。
義弘に比べ少々知名度の低い義久ですが、そこには本宗家の当主として我が侭で一筋縄ではいかない一族・一門・国衆等の有力家臣団を纏めあげ、朝鮮出兵・関ヶ原を切り抜け、おそらくとても統治しにくい体制だった戦国期の島津氏を、家を存続に導いた…と言っても過言ではないのです。
そこには他国の統治機構と比較しても大きく違う、独自の支配体制であり、義久の手腕があってこそ成り立っていたものでした。 こういうと何だか難しい話の様に聞こえますが、そこはさすが数々の講演、講座をこなした新名先生、島津を扱った漫画・小説等の作品を切り口に始まり、室町期の島津氏から最新の戦国島津氏の研究も抑えつつ、核心に迫る部分まで、初心者からマニアまで非常にわかり易く解説されました。
 講演台に置かれているのは戎光祥出版刊「島津貴久」
講演台に置かれているのは戎光祥出版刊「島津貴久」その他、著書「島津貴久」についてや、他の研究者の島津史関係新書、ヤングマガジン連載「センゴク権兵衛」について、書評を書かれた「忠義に死す 島津豊久」についてなど、戦国島津界隈全体の動きについても話題が及びました。
その後は新名氏、編集長丸山氏、司会の石渡氏を交えての座談会。新名先生は日置市から贈呈されたという島津家家紋の陣羽織を羽織って登場! 島津氏を研究するきっかけ、書籍発刊にあたってのエピソード、今後どのような書籍が発刊される予定なのか? など、普段は中々聞けない話が飛び出し、大いに盛り上がりました。 座談会終了後は会場内で販売してる書籍購入者へのサイン会。会場後方までずらーっと続く長蛇の列ができていました。
 陣羽織を羽織り気迫を漲らせサインに臨む新名先生
陣羽織を羽織り気迫を漲らせサインに臨む新名先生
このような機会を与えて下さった戎光祥出版の皆様、新名先生に感謝致します。大変有意義で勉強になりました。第2弾、第3弾を期待しています!