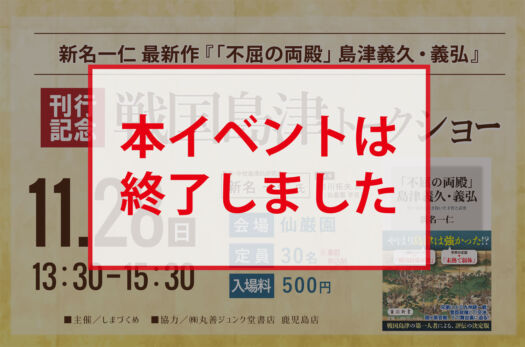新名:他家にここまで詳しい日記を書いた家臣がいないので、単純に比較はできませんが、当時の島津家中では当然なのでしょう。ドイツの人が水がわりにビールを飲むのと同じ感覚のような気もします。加えて、今のように醸造技術が発達してませんので、アルコール度数はさほど高く無いようにも思います。
── 確かに、二日酔いの記述は少ないですね(笑)。日常的な飲酒にはもちろん嗜好という面もあると思いますが、多くは「寄合」の中でのことですし、「地頭衆中制」という支配体制・「談合」の重視、という戦国島津氏の特性を考えると、重要な意思疎通の手段なのかな、とも感じました。
新名:もちろんそういう側面があるでしょう。当時の意思疎通手段は書状とそれを持参する使者の口上しかありませんでした。それだけだと家中間の結束は生まれませんし、お互いの本音も伝わりづらいです。大所帯となった家中内にはさまざまな派閥もあったでしょうし、「寄合」は公的な「談合」とは異なり、酒がはいってリラックスできる場でしょうから、お互いの本心を知ることができる貴重な機会です。お互いの本音を探り合い、結束を深めることが大きな目的のひとつなのでしょう。
── 酒のほかは、風呂の記述も目立ちますね、これもまた薩摩らしさを感じます。覚兼が各所の風呂廻りに飽き足らず宮崎城内に造作し始めるのが面白いです。風呂を「焼く」という表現が散見されますが、焼いた石などに水をかけ蒸気を発生させているということでしょうか。
新名:日記でははっきりしないのですが、現在各地で復元されている蒸し風呂を見ますと、大釜で御湯を沸かし、その上にすのこを敷いた小屋をかけてそこに入るようです。なぜ「湧かす」「焚く」じゃなくて、「焼く」なのは言語学の方に聞いてみたいですね。

天正11年1月、肥後より帰国中に覚兼は湯治のため湯の村(現 湯之元温泉)に立ち寄る。江戸初期に浴場として本格的に整備され、藩直営となってからは身分により入浴場所が御前湯・地頭湯・所湯・打込湯と分けられていた。写真は温泉街を代表する「元湯・打込湯」(鹿児島県日置市東市来町)。
── 戦国期島津氏の大きな特徴といえば「鬮 」や「神慮の重視」ですが、今回の日記にも登場しますね。これらについて新名先生は前著「島津四兄弟の九州統一戦」(星海社)で、意見調整や政策決定の合理化・大義付けとしての側面があることを指摘されていますが、その成立には「神威」が家臣団に浸透していることが前提となるかと思います。実際、日記の中でも島津家中の信心深さが散見されますが、その背景はどこにあるのでしょうか。
新名:一つには島津四兄弟の祖父・島津日新斎(忠良)の影響があるでしょう。いわゆる「ナメられたら殺す」という中世武士の士風が蔓延し、良く言えば「勇猛果敢な尚武の気風」、悪く言えば直情径行で殺伐とした島津家中をコントロールするために日新斎が作り出したのが有名な「いろは歌」ですが、その中で神仏に対する崇敬を説いています。
「仏神他にましまさず 人よりも心に恥ぢよ 天地よく知る」
(意訳:人の心には神仏が住んでいる。心に恥じぬ行動をせよ。誰も見ていないようで、天地は見ている。欺くことはできない)
「ねがわずば 隔へだてもあらじ いつわりの 世にまことある 伊勢の神垣」
(意訳:如何に嘘偽りの多い世であっても、無理な欲望を持たなければ神は公平に扱って下さる)
この他にも、島津家中の行動規範には「いろは歌」の教えが色濃く反映されています。例えば日新斎以来、島津氏は大きな合戦で勝利した後は敵味方問わず施餓鬼を行い、供養のため六地蔵塔を建立していますが、これらはいろは歌で説かれる死者への尊厳に基づいています。また、主君のために命を捨て去る覚悟を常日頃から持つことの必要性も説いており、これは島津家中の死を恐れぬ勇猛さに繋がっています。
義久や義弘が家臣らを説得・統制する際の常套手段として度々日新斎の教えを説くのも、日新斎が家中における精神的支柱・カリスマとして機能していた証ということだと考えられます。

「堅志田城址」(熊本県下益城郡美里町)。独断による甲斐氏との手切れについて「神慮を蔑ろにするとは曲事である」と義久から叱責を受けた覚兼ら老中は、天正11年10月の堅志田方面再攻撃に際し義久の指示通り鬮を引いて作戦を決定している。なお島津軍は天正13年に堅志田城を攻略するが、この時にも現地部隊が独断専行(若衆中による命令無視の突出)を犯している。
── なるほど、神慮を重視する姿勢含め、戦国島津氏のいわば「志向」を形作ったのが「いろは歌」、そして日新斎ということですね。
家中の価値観という面で興味深いと思ったのが、覚兼が各人が戦場でうけた「疵」について度々言及している点です。日記では士卒が挙げた軍功について詳細に記していますが、その記述からは「分捕り(敵の首を獲ること) 」と、戦闘による負傷がまるで同等の価値があるかのような印象さえ受けます。
更にはそうした疵を「痛がらない」ことにも重きを置いていますよね。例えば天正10年12月7日の日記では、覚兼弟・鎌田兼政が負傷しても痛がらなかったとして、伊集院忠棟はわざわざ祝言まで送っている。
新名:「外聞」「自他国之覚」という名誉をもっとも重要な徳目とする島津家中としては、痛がらないことが極めて重視されるのだと思います。痛がるものが出ると士気が下がり、全体に恐怖心・パニックが広がるという問題もあるのでしょう。
例えば弘治3年(1557)の蒲生氏・菱刈氏との合戦で、島津歳久は左腿を矢が貫通する重傷を負っていますが、「当所好く候て御痛なし(当たり所が良かったので、痛がらなかった)」と記されています。(『山本氏日記』)。命に別状が無い=当たり所が良かった、ということなのでしょうが、どう考えても痛くないはずがない。しかしそれを表に出さないことが矜持であり、武名を高めるという認識があったのだと思います。
そうした価値観は戦闘以外の日常においても同様です。天正13年(1585)4月、覚兼は妹婿にあたる吉利忠澄に狩りに誘われ、領地に赴きます。その狩りにおいて一行は大猪と遭遇し、飛び掛かられた忠澄は3ヶ所を噛みつかれてしまいますが、やはり痛がらなかったと(『上井覚兼日記』)。更に翌日、帰ろうとした覚兼らに対し「私の負傷が原因で急いで帰ったと噂が立つと自分の『外聞』が良くない。少しも痛くないので今日はこちらに留まり、帰るのは明日にしてほしい」と要請しています。
狩りには現地住民が多数参加しており、地頭として「痛みで狩りが中止になった」とするわけにはいかなかったのでしょう。覚兼はこの要請に応え出発を遅らせており、「外聞」を保つことの重要性が家中において共通認識であったことが伺えます。