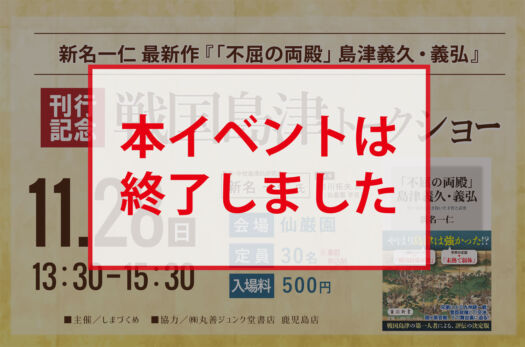2.豊臣政権の人身御供 ~従弟たちとの二度の結婚
一般に中世や戦国期の史料では、女性の情報が極端に少ない。それは亀寿も例外ではない。そんななか、彼女が成人した前後の動向の一端がわかる出来事がある。島津氏は天正九年(1581)、肥後南部の相良氏を屈服させると、本格的な北上作戦を開始した。同十一年(1583)三月頃には、義久は肥後八代を北上作戦の拠点にし、弟の義弘(当時、忠平)に日向真幸院から所替えしてもらおうと考えて、居城の内城(現・鹿児島市大竜町)に招いて説得した。
このとき、亀寿も義弘をわざわざ招いて女房衆とともにささやかな宴席をしている。
奥向きの亀寿がなぜわざわざ叔父の義弘を接待したのか不明だが、八代所替えを頑なに拒む義弘を、義久が何とか軟化させようとした策だったのかもしれない。

「内城址」(鹿児島市大竜町)。別名「御内」とも。天文19年(1550)に築かれ、島津貴久は一宇治城より居城を移す。以後、鶴丸城が築かれるまで50余年、島津氏の拠点となった。廃城後は島津氏に仕えた高僧・南浦文之の開山により大龍寺が建てられた。廃仏毀釈により廃寺となり、現在跡地は大竜小学校となっている。
以降、亀寿の動向はほとんど不明で、改めて史料に登場するのは、島津氏が豊臣秀吉に降伏してからである。
同十五年(1587)五月八日、太守義久は秀吉に降伏した。それに伴い、剃髪して龍伯と名乗ることになった。
降伏とともに、秀吉は人質を出すように命じた。義久は手許にいた亀寿を差し出さざるをえなくなった。秀吉の本陣である川内の泰平寺で亀寿を引見したとき、秀吉は偽者ではないかと疑ったという説がある(『薩藩旧伝集』補遺)。
「秀吉公が九州下向のとき、太平寺で『おかち様』が人質としておいでになったとき、秀吉公は偽者かとお疑い、ご容貌が美しいので、なおさら訝しくお思いになって、御前にあった菓子が入った壺を大げさに投げ出したところ、(亀寿は)少しも驚きなさらないで一目見ただけだった。そのとき(秀吉は)龍伯の実子だと仰せになった」
亀寿と思しき人物の名前を「おかち」(「おかじ」か)と書き、美人だったとしているのは注目されるが、当時、亀寿は十七歳で立派に成人している。菓子などに飛びつく年齢ではない。この逸話は後世の創作だろう。
亀寿は人質として上京する。結局、在京期間は慶長五年(1600)の関ヶ原合戦までの十四年間の長きにわたった。その間、一度だけ帰国している。
義久は亀寿を同行して上京した。一年ほど経った天正十六年(1588)六月、国許から弟の義弘が上京してきたので、入れ替わりに義久が八月に帰国することになった。このとき、愛する娘との別れを悲しんだ和歌を上方で友人になった細川幽斎に贈った。
「二世とはちぎらぬものを親と子の わかれん袖のあはれをもしれ」
これに対する幽斎の返歌は
「馴〳〵し身をばはなたし玉手箱 二世とかけぬ中にはありとも」
「二世」とはあの世とこの世のことであり、義久は亀寿との別れが今生の別れになるかもしれないと覚悟して、袖を濡らしている。
一方幽斎は、あの世とこの世とでは決して契れぬ仲なのに、ずっと慣れ親しんだ「玉手箱」を手放すのは身がちぎれるほどつらいでしょう、と返したのである。「玉手箱」とは美しい箱という意味だが、ここでは亀寿に喩えられている。古今伝受の和歌の達人ならではの寓意で、義久の亀寿への想いのほどを見事に言い当てている。
このやりとりには続きがある。幽斎は義久に同情して義久の和歌を秀吉に披露したのである。すると、秀吉も憐れみを感じたのか、義久に亀寿を連れて帰国してよいと許可を出してくれた。
一見すれば、義久の和歌は恋歌と見まがうほどだが、義久の亀寿への目も入れても痛くないほどの愛おしさが伝わってくる。義久が亀寿を「至極の御愛子」だと思っていたとする後世の評は決して大げさではなかったことがわかる。
愛しき亀寿も成長して配偶者を決める時期になった。よく知られているように、相手は叔父義弘の嫡男又一郎久保である。縁組の時期ははっきりと確定できないが、遅くとも天正十七年(1589)二月までに行われた。二人はともに在京していたいとこ同士で、亀寿が二歳年上だった。同年に縁組だったとすれば、亀寿十九歳、久保十七歳である。
この縁組は関白秀吉のお声がかりだった。義久が二年後に久保付きの家臣、川上経久に宛てた書状に「関白様より縁重并に家婚の儀仰せ定められ、尤も珍重に候」とある(『玉里島津家史料一』1)。このことから、「縁重」は久保が義久の養子になることであり、二人の縁組も義久の意向ではなく、秀吉の命令だったことがわかる。
その後、久保は秀吉の小姓の列に加えられ、小田原の陣のときには太刀持ちの役をつとめた。増水する富士川を瀬踏みのため渡河する役を負い、見事に渡河してみせたので、秀吉も「感じ玉ふこと斜めならず」と褒め称えたという(『後編二』629)。
秀吉の命令だったとはいえ、二人の仲は睦まじかった。同十九年三月、在京の義弘が国許の夫人宰相殿(実窓夫人)に宛てた書状には「又一郎夫婦の間はよいと聞いている」と知らせている。
二人の間に男子が誕生して成長すれば、島津家の家督問題はのちに迷走することはなかったかもしれない。残念ながら子どもが誕生することもなく、文禄元年(1592)、久保は父義弘とともに朝鮮に出兵した。しかし、翌二年九月八日、久保は病死してしまう。弱冠二十一歳の若さだった。
異国の地で夫が他界したことを知らされた亀寿の悲しみはいかばかりだっただろうか。
しかし、亀寿が悲しみに浸る間もなく、秀吉から非情な命令が下った。国許にいる久保の弟又八郎忠恒に急ぎ上京を命じると、翌三年六月、亀寿との縁組を命じたのである(『後編二』1326)。久保死去からまだ一周忌も迎えていなかった。義久が亀寿の再婚をどのように感じたのかは不明だが、島津家の将来のためには致し方ないと思ったのかもしれない。
忠恒は亀寿より五歳年下だった。この年、亀寿は二十四歳、忠恒十九歳だった。忠恒も五歳年上の姉さん女房で、しかも亡兄の妻を娶るのは秀吉の命令とはいえ、困惑したのではないだろうか。
ここで注目すべきは、久保・忠恒の兄弟が相次いで亀寿と縁組したことの意味である。これはやはり、亀寿の配偶者こそ、島津家の次の家督候補に擬せられていたことを示している。もっとも、それは義久の意向よりも豊臣政権の意向の意味合いが強かったのかもしれない。
しかし、亀寿もまた亡夫久保の一周忌法要も行えないままの忠恒との再婚には乗り気ではなかったことは明らかだった。久保とは京都で共に人質として数年過ごしており、同じ境遇同士で心が通じ合うことがあったはずである。
一方、忠恒とはもともと疎遠な間柄だった。いとこ同士とはいえ、亀寿は鹿児島の内城、忠恒は日向真幸院の飯野で育っていた関係から、ほとんど会ったこともなかったのではないか。また忠恒は義久や義弘に注意されたように、振る舞いが粗野な面があり、それも亀寿の忌避するところだったかもしれない。
のち江戸時代後期、儒者の山本正誼が著して、島津家の正史とも評される『島津国史』巻二十四には「世間では、夫人(亀寿)と公(忠恒=家久)は琴瑟和せずと伝えられていた」と書き記している。琴瑟とは夫婦仲が睦まじいことの喩えだが、それが「和せず」なのだから、二人は不仲だったと公式に認めているのである。
もっとも、忠恒のために弁護すれば、上京して慌ただしく縁組すると、すぐさま久保の代わりに朝鮮に出陣しているから、ほとんど夫婦生活もなかったと思われる。
3.孤独と病気がちな人質生活
新しい夫、忠恒不在の間、伏見にいた亀寿のまわりには姑の宰相殿くらいしか親族がいなかった。父義久も肥前名護屋城に詰めていることが多かった。慶長三年(1598)四月、義久は重臣たちとともに、不思議な行動に出た。京都東山に泉涌寺という寺院がある。天皇家の菩提寺として知られているが、その塔頭のひとつに今熊野観音寺がある。義久たちはここに参詣して逆修墓を建立した。
現地を訪れたことがある。真ん中の高さ2メートル以上ある大きな五輪塔を中心に五基の墓石が並んでいた。五輪塔の両脇に頭に円形の石を頂いているのは月輪塔と呼ばれる形式の墓石である。石材はすべて薩摩特産の山川石だった。

-640x427.jpg)

「今熊野観音寺」(京都市東山区泉涌寺)の亀寿逆修墓。「藤原氏島津義久」の刻銘が確認できる(3枚目)。なお島津氏は近世になり清和源氏を公称するまでは藤原姓を名乗っていた。