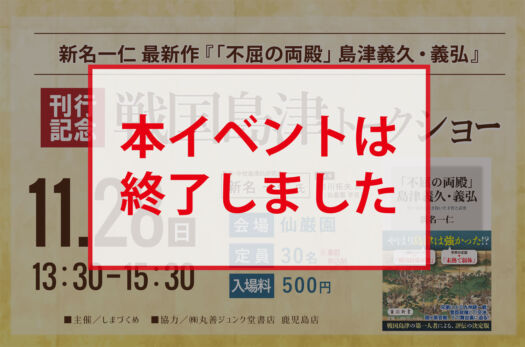逆修とは本来、生きているうちに、あらかじめ死後の冥福を祈って仏事を行なうことを意味する。義久は当時、六十七歳の老境にあり、自分の逆修墓を建立してもおかしくない。しかし、これは少し特殊だった。その五輪塔の造主はたしかに義久で、右横に「藤原氏島津義久」と刻んである。だが、逆修の対象は「□□彭摠逆修 慶長三年戊戌」と刻んであった。頭二文字は剥落して読み取れないが、亀寿の法号が「持明彭摠庵主」であることを考えると、剥落した二文字は「持明」であることは間違いない。
この逆修墓の意味するところは、義久が亀寿の長寿や健康を祈願して建立したということだろう。
なお、左脇の月輪塔には「宗参覚阿逆修 慶長三年卯月下一日」とし、「薩州住平田太郎左衛門尉増宗」と刻んである。これは義久の家老、平田増宗が自分のために造立した逆修墓だった。
ところで、なぜ義久が亀寿のために逆修墓を造立したのだろうか。それはおそらく亀寿の体調不良を心配したためだろう。逆修墓造立の少し前の三月七日付で、義久が朝鮮在陣中の忠恒に宛てた書状があり、次のように書かれている(『後編三』385)
「一、そもじ(忠恒)のうもじ(内方=亀寿)はこの間、絶えず不食で、そのような具合である。然るに、二月二十四日の夜より俄に危機に陥るほどの煩いになった。翌二十五日には一大事のように見えたけれども、いろいろ手を尽くして、祈念立願を精一杯行ったので、この頃はよくなった。ご安心下さい」
亀寿は何らかの理由から不食状態が続き、非常に危険な状態に陥ったが、懸命に手当てしたので、何とか一命を取り留めたというのである。
義久は亀寿への治療を尽くしただけでなく、「祈念立願」したとあるから、神仏に願かけもしている。これが逆修墓を造立するという立願だったのではないだろうか。
十数年の長きにわたる上方での人質生活と先夫久保の死去を看取れなかった悔恨は、亀寿の心身を蝕んでいたのかもしれない。そうした亀寿の生きるよすがとなったのは、生母種子島氏の供養墓へ詣でることだったのではないだろうか。
洛中の真ん中に本能寺がある。織田信長が明智光秀の謀叛で落命した舞台になった、あまりにも有名な寺院である。本能寺の変当時の同寺は四条坊門通西洞院にあったが、豊臣秀吉の京都改造によって、寺町(現・中京区寺町通御池下ル)に移転した。この移転した本能寺の境内にある信長供養塔の左側に三基の宝篋印塔が縦に並んでいる。その一番奥にある墓が注目で、表に法号は「円信院殿妙蓮幽儀」と刻んである。命日もあり、元亀三年(1572)十二月二十三日である。これに該当するのは、義久の後妻で亀寿の生母にあたる種子島氏(父は種子島時尭、母は島津日新斎三女)である。

「法華宗本門流本山の本能寺」(京都市中京区下本能寺前町)の亀寿生母・種子島時尭女(島津義久後室)の墓。
なぜ亀寿の生母の墓が本能寺にあるのか。本能寺は法華宗本門流の本山であり、種子島氏の菩提寺である本源寺(西之表市)はその末寺だった縁からだろう。なお、一説によれば、生母種子島氏は京都で卒去したという(「末川家文書 家譜」)。その真偽は不明である。
この供養塔の施主は亀寿ではないかと考えている。ずっと在京している亀寿は亡母の命日などの追善供養ができない。そのため、本山にあたる本能寺に供養墓を建立したのだろう。
以前、同寺の寺務所に問い合わせたが、過去帳も失われており、詳細は不明との回答だった。ただ、わずかながら痕跡がないわけではない。同寺の史料に「奉寄進御経三十部 為悲母妙蓮霊魂」という奉納帳があり、年次が文禄四年(1595)五月十二日で、施主が「藤女」となっている。
一説によれば、これは亀寿生母の法号「妙蓮」と一致しており、亀寿が在京中の時期である。施主についても、当時、島津氏は藤原を名乗っていたので亀寿の可能性もあるかもしれない(『本能寺史料 中世篇』214)。
いずれにせよ、病気やストレスに悩まされる亀寿にとって、母を供養することは心の安寧をもたらすよすがだったのかもしれない。
亀寿が病気を煩った史料はまだある。慶長五年(1600)三月二十九日、在伏見の義弘が国許の忠恒に送った書状には「御かみ様(亀寿)はこの頃小脳気で、まだご快気していない」とあった。「脳気」とは頭痛がして気分がすぐれない症状である。
義弘は念のため、谷杉という祈祷師に占わせたところ、「女の呪詛のたたり」が原因だという。また帰化明人の江夏友賢に卜占させたら、寿命に障りがあるようなことではないし、火急の煩いでもないから安心してもよいと答えた、と忠恒に伝えている(『後編三』1078)。
義弘が亀寿の症状を心配して、医者だけでなく卜占にも頼ったところを見ると、亀寿の様子が尋常ではなく、たとえば狐憑きのような一種の精神朦朧状態にあったのではないだろうか。
亀寿の記事があまり史料に表れないなかで、病気の記事が意外と多いのは、亀寿は長期にわたって心身ともに不調な生活をしていたことを示している。
なお、当時の亀寿の居所だが、文禄四年(1595)のいわゆる秀次事件後、聚楽第が解体されると、亀寿は伏見に移っている。伏見にあった一柳氏旧邸を秀吉から与えられている(『後編二』1629)。当主の一橋直末が小田原陣で戦死して同家が断絶しているから、その旧邸かもしれない。
4.関ヶ原合戦に巻き込まれて ~危機一髪の帰国行
亀寿にとって、その生涯で生死に関わる最大の危機はやはり関ヶ原合戦である。西軍が挙兵したときに伏見城下の島津屋敷にいたから、舅の義弘と宰相殿夫妻や主従のみならず、亀寿も否応なく巻き込まれたのである。
伏見城址(京都市伏見区桃山町)。写真は2004年に閉園した遊園地の施設として建設された模擬天守(現在天守内は立ち入り不可)。

かつての伏見城下、桃山町には「桃山町島津」の地名が残る。佐土原島津家(島津以久系)の屋敷跡とされているが、城に近く佐土原家の屋敷にしては広大すぎるので、関ヶ原以前は本宗家の屋敷だった可能性がある。
大坂城が挙兵した西軍に占領されたのは慶長五年(1600)七月十三日である。伏見城に徳川方が籠城している以上、大坂と伏見の間は一触即発だった。義弘は家康の要請により伏見入城を試みたとされるが、結局、実現していない。ともあれ、兵力で優勢なうえ、上方を制圧するつもりである西軍が伏見城に押し寄せてくるのは時間の問題だった。
義弘も亀寿や宰相殿などをどこに避難させるべきか、対応に苦慮していた。十四日、義弘が国許の義久と忠恒に送った書状で「尚々、かみさま(亀寿)のご進退、どこへ移すべきか談合の最中です」と述べている(『後編三』1122、1125)。
それでも、義弘は遅くとも同月二十九日までに亀寿を大坂に移している。亀寿の安全のためには西軍に従うしか選択肢がなかったのである。一度は家康から伏見城の留守居を命じられたにもかかわらず、義弘が方針転換せざるをえなかったのは、東西両軍のどちらについたら有利かという政治的な判断よりも、亀寿の安全を図るという内向きの事情が最優先だったことを示している。
義弘がここまで亀寿の安全にこだわるのはなぜか。それは亀寿に万が一のことがあれば、たちまち息子の忠恒の家督相続に影響を与えるからだった。
忠恒の家督相続の時期は確定できないが、早ければ文禄三年(1594)四月、朝鮮に出陣する頃、義久と義弘の命で家督相続したとされる(『島津家文書之二』1139)。遅くとも慶長四年(1599)一月の近衛少将任官までだろう。
しかし、亀寿が死去したら、義久の悲嘆と激怒は想像に難くなく、忠恒家督の正統性は失われる可能性があった。義弘はそれを承知していたからこそ、不本意ながらも西軍に付かざるをえなかったのだろう。
結局、慶長五年(1600)九月十五日、関ヶ原の決戦はたった一日で決着、西軍の敗北だった。義弘主従が有名な「島津の退き口」で撤退した。そして五日後の二十日、義弘主従は苦難の末ようやく泉州堺にたどり着いた。亀寿が義弘の安否を知ったのは翌二十一日だと思われる。
義弘は道具衆の横山休内をひそかに大坂城に派遣していた。休内は義弘から鎧を拝領しており、それを着して亀寿に面会した。すでに義弘戦死の噂が広まっていたので、亀寿は優しい舅の存命を知って、うれしさのあまり休内を引見して盃を与えたほどだった(「新納忠元勲功記」)。
その後、亀寿たちは大坂脱出の算段をした。亀寿や宰相殿は人質として城下の屋敷から城内に移されて軟禁状態にあった。そのため、脱出したのちに義弘主従と大坂湾で共に船で合流することに打ち合わせていた。
城外に出られる手形は一通しか得られなかった。お付きの僧侶が義弘が戦死したので人質を帰国させてほしいと訴えて、ようやく夫人の宰相殿だけに下付された(「瀬戸口休五郎覚書」)。
父義久と夫忠恒が国許だったため亀寿宛ての手形を入手できなかったので、亀寿の身代わりを立て、亀寿は宰相殿の侍女に扮して脱出することになった。
しかし、亀寿が密かに脱出したとなると、その責を問われかねない。そのために身代わりを立てることになった。選ばれたのは亀寿付きの家来、大田忠秀の娘お松だった。もし露見したら命はないかもしれない。お松も決死の覚悟で引き受けたのだろう。
二十二日、亀寿一行と義弘主従はともに舟行して、兵庫川口(西ノ宮沖)で落ち合った。このとき、宰相殿は茶道具の名物である平野肩衝を袂に入れ、亀寿は島津家の系図を懐に入れていた。二人が島津家の家宝を大事に持参していたので、義弘も大いに喜んだ(「惟新公関原御合戦記」)。
その後は順調に瀬戸内の海を進んだが、異変が起きたのは瀬戸内を抜けた豊後沖だった。国東半島の南の付け根に守江湾がある。当時、黒田如水の水軍が同湾の周辺に集結していた。
義弘たちの船団(艘数不明)がこの海域を通りかかったのは二十七日の夜だった。義弘の乗る先頭の船の提灯の明かりを目印に進んでいた。ところが、深夜に強風が吹き荒れ、後ろの三艘が遅れ出し、提灯の灯火を見失って方角がわからなくなった。三艘は守江湾に停泊していた黒田水軍の篝火を提灯と勘違いして接近したため、ついに同水軍に見つかり、海戦となった。三艘のうち一艘は宰相殿の御座船だった。残りの二艘が宰相殿の御座船を逃がすために必死に抗戦した末に全滅してしまった(『新訂黒田家譜一』)。
じつは、この二艘のうちの一艘は本来、亀寿の御座船だった。義弘は航海の前途で不測の事態が起こるかもしれないと、事前に亀寿を自分の御座船に移していた。義弘の直感が亀寿を救ったのである。もし乗り移っていなかったら、亀寿は自害したかもしれない。まさに危機一髪だった。
こうした苦難の末、二十九日朝、義弘一行の船は日向細島に着いた。あとは陸路で帰国するだけだったが、またしても一難あり。義弘一行が佐土原城に着いた前後、島津氏とは永年敵対関係にあった飫肥の伊東氏の家来たちが旧領回復めざして挙兵し、西軍に属した高橋元種(日向延岡城主)の支城、宮崎城を攻略して佐土原城に迫る勢いを示した。
そのため、義弘は亀寿と宰相殿の安全を図るため、迂回路を進ませる別行動をとったほどだった。
一行が太守義久の富隈城に着いたのは十月三日である。義弘主従はじつに十九日、亀寿たちも十二日かかった逃避行だった。亀寿や義弘と再会した義久は喜びを語った(「惟新公関原御合戦記」)。
「足下(義弘)は今般大敵の囲みを破って、身を全うするのみならず、大坂にいた人質以下の子女をことごとく携えて帰国したことは、庸将の及ぶところではない」
控えめな記述だが、義久が亀寿の帰国を喜んだことが伝わってくる。
亀寿、孤独と波瀾の生涯(前編)了 → 後編
プロフィール
桐野作人
1954年鹿児島県生まれ。歴史作家、武蔵野大学政治経済研究所客員研究員。
歴史関係の出版社編集長を経て独立。戦国・織豊期や幕末維新期を中心に執筆・講演活動を行う。
主な著書に『関ヶ原 島津退き口』、『さつま人国誌 戦国・近世編1~3』、『織田信長―戦国最強の軍事カリスマ―』、『だれが信長を殺したのか』、『薩摩の密偵 桐野利秋』など多数。
2019年、『龍馬暗殺』で第29回高知出版学術賞特別賞を受賞。
添田一平 WEB / Twitter
フリーランスのイラストレーター。福岡県出身。東京学芸大学卒業。
歴史、特に甲冑武具についての研究を能くし、時代考証や歴史的根拠に基づいた絵を得意とする。2021年現在は猫2匹と共に京都に住む。一般社団法人 日本甲冑武具研究保存会 近畿支部会員。